【耳鼻咽喉科医が解説】「聞こえづらいかも…?」放置厳禁!難聴の原因と補聴器で生活の質を向上させる方法
- 耳鼻咽喉科

前回のブログでは、加齢とともに誰にでも起こりうる「難聴」が、放置すると様々なリスクにつながることをお話ししました。今回は、その聞こえづらさに対処するための重要な選択肢である「補聴器」について、もう少し詳しくご紹介したいと思います。
補聴器の正しい理解から始めましょう
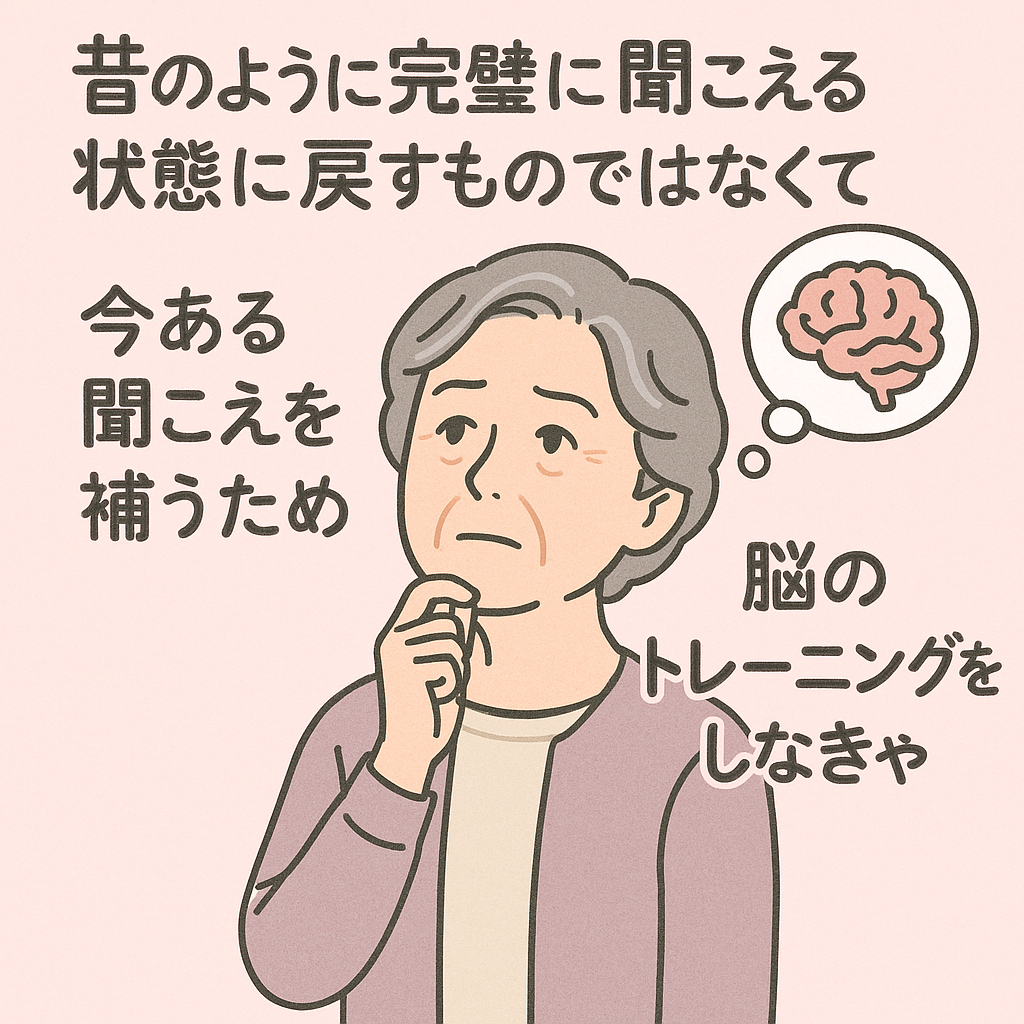
皆さんは補聴器にどんなイメージをお持ちでしょうか?「つけても聞こえが元通りにならない」「雑音がうるさい」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。まずお伝えしたいのは、補聴器は「昔のように完璧に聞こえる状態に戻す」ものではないということです。
補聴器は、あくまで「今ある聞こえを補う」ための医療機器です。そして、正しく使いこなし、聞き取りに慣れるためには、脳のトレーニングが必要なものと考えていただくことが大切です。
テレビCMなどで「集音器」を見かけることもありますが、これは補聴器とは全く異なります。
集音器はすべての音をただ大きくする「オーディオ機器」で、一人一人の難聴の状態に合わせて調整する機能はありません。
一方、補聴器は厚生労働省に「医療機器」として承認されており、医師の診断のもとに、その方に合った細かい調整を行うことができる点が大きな違いです。
補聴器購入へのステップ
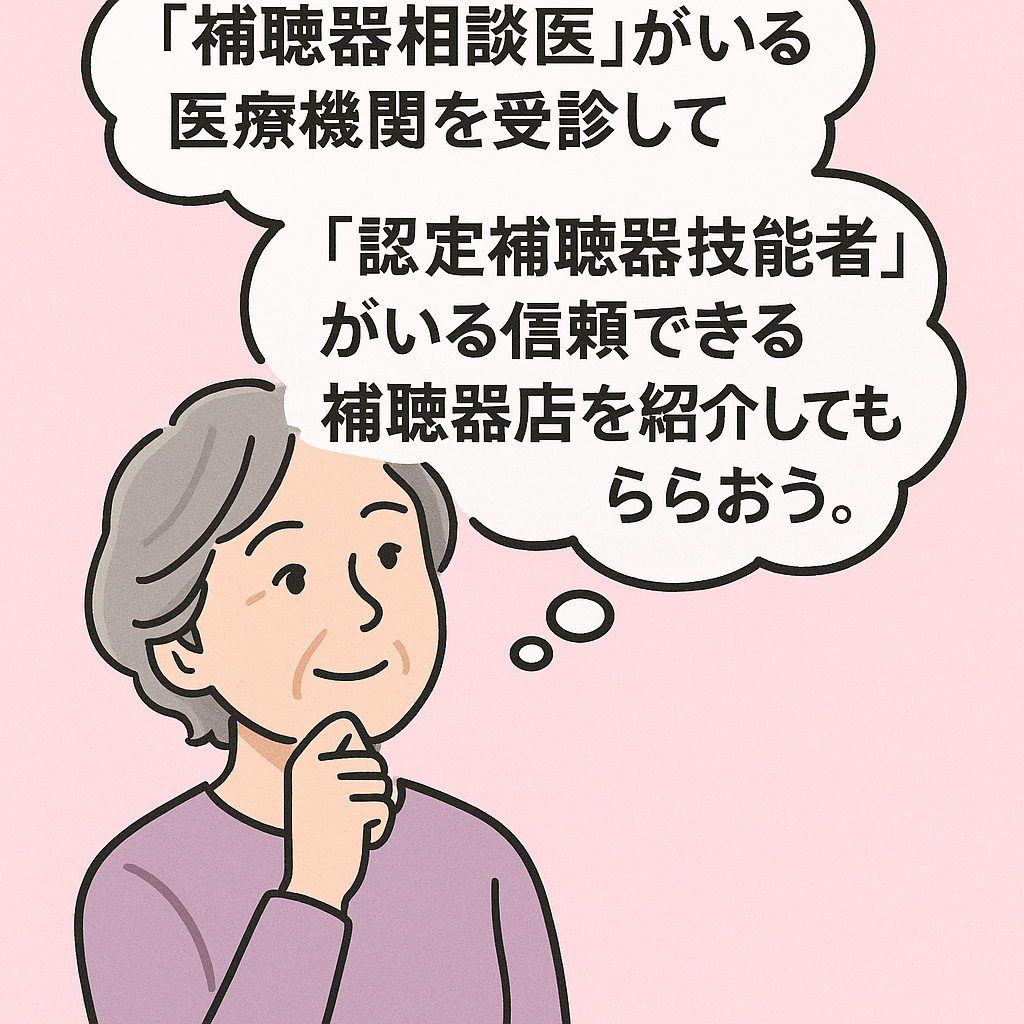
聞こえに不安を感じたら、まず「耳鼻咽喉科を受診する」ことが非常に重要です。
聞こえづらさの原因が、単なる加齢によるものか、あるいは治療が必要な別の病気によるものかを正確に診断するためです。
加齢性難聴と診断された場合に、医師から補聴器についての専門的なアドバイスを受けることができます。
補聴器を検討されている場合は、「補聴器相談医」という資格を持つ医師がいる医療機関を受診するのがおすすめです。
補聴器相談医は、その方の聞こえの状態をしっかり判断し、「認定補聴器技能者」がいる信頼できる補聴器店を紹介してくれます。
認定補聴器技能者は、医師の検査結果に基づき、一人一人の聞こえに合わせて補聴器を精密に調整する専門家です。
補聴器は残念ながら健康保険は適用されません。

しかし、補聴器相談医が作成する「補聴器適合に関する診療情報提供書」があれば、医療費控除の対象となります。
また、自治体によっては補助金制度がある場合もありますので、確認してみると良いでしょう。
補聴器に慣れるための「脳のトレーニング」
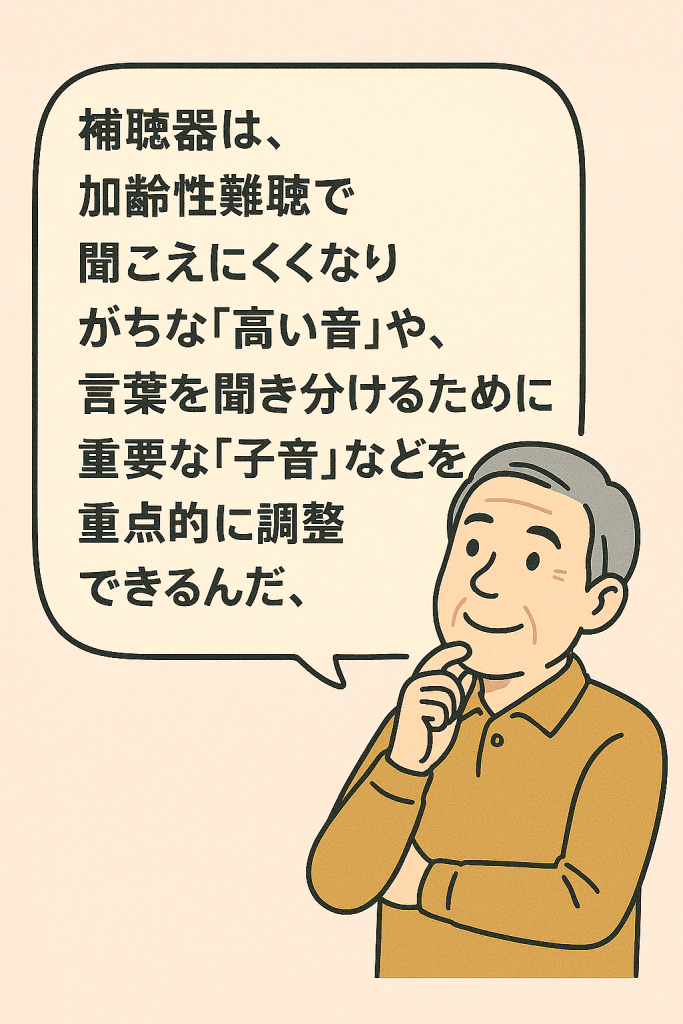
補聴器は、加齢性難聴で聞こえにくくなりがちな「高い音」や、言葉を聞き分けるために重要な「子音」などを重点的に調整できます。
しかし、細かく調整しても、使い始めたばかりの頃は違和感があるものです。
これは、補聴器から入ってくる新しい音に「脳が慣れていく」ための期間が必要だからです。脳が順応するには通常2~3ヶ月かかると言われています。

この「脳のトレーニング」を成功させるための大切なポイントは3つあります。
1.起きているときは、基本的には補聴器をつける。
最初は食器の音やエアコンの音などがうるさく感じても、慣れることが重要です。
「1日10時間以上」を目安に装用し、最初は「少しうるさいけれど我慢できる」レベルから始めて、徐々に慣らしていくのが良いでしょう。
2.定期的に調整する。
慣れてきたら、1~2週間に1回程度、補聴器店で調整を繰り返します。これを続けることで、2~3ヶ月後にはご自身に合った最適な調整ができます。
3.聞こえを確認する。
音の大きさだけでなく、言葉がどれだけ聞き取れているかを客観的に確認することも大切です。前回のブログでご紹介したセルフチェックなども活用できます。
補聴器を使うことのメリット
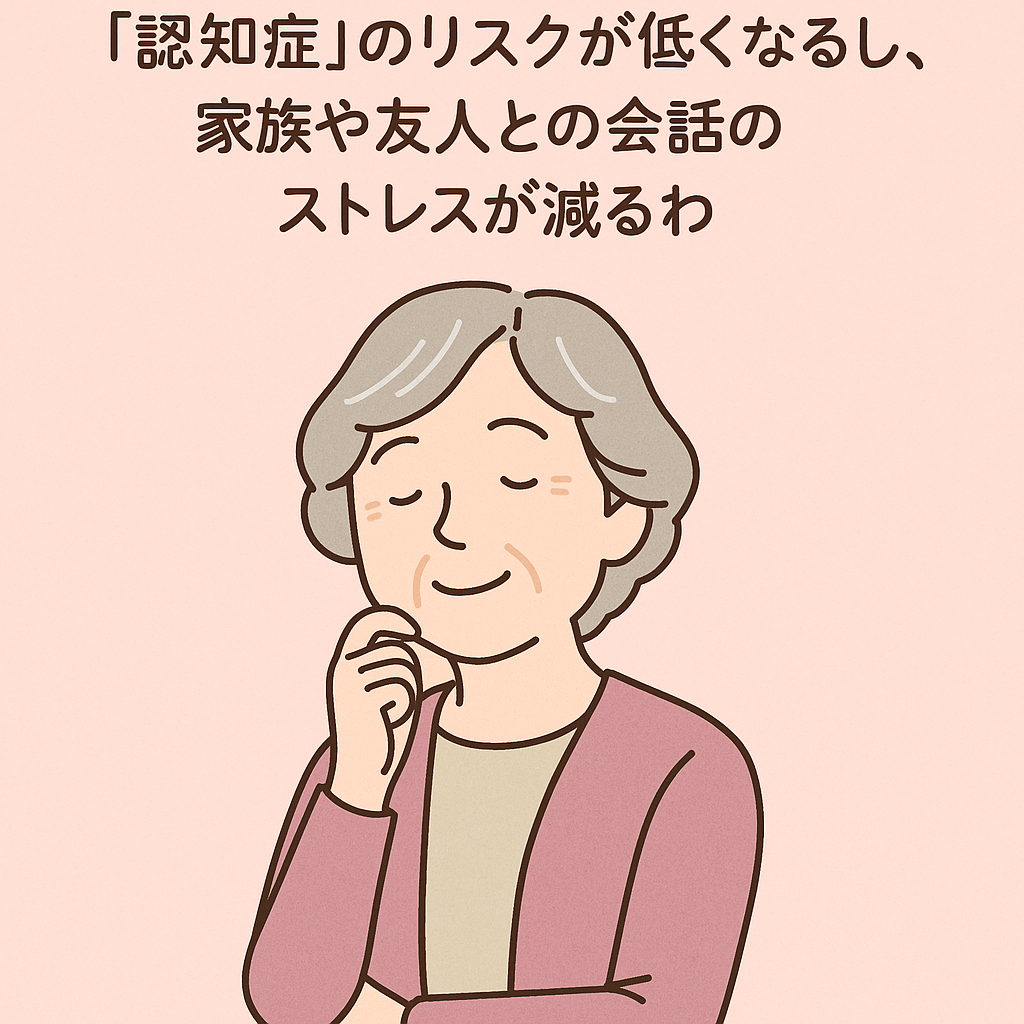
補聴器を使って会話をしっかり理解することは、脳の活性化につながり、「認知症」のリスクを低くする効果が報告されています。また、ご家族や友人とのコミュニケーションがスムーズになり、会話のストレスが減ることで、お互いの関係性がより良好になることにもつながります。
まとめ
補聴器は、ご自身の聞こえの状態に合わせて調整が必要な医療機器です。使い始めは慣れるのに時間がかかるかもしれませんが、根気強く続けることで、生活の質を大きく向上させ、将来の健康にも良い影響を与えます。
当院には補聴器相談医がおります。
聞こえについて気になることや、補聴器について不安なことがあれば、どうぞお気軽に当院にご相談ください。
